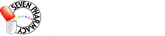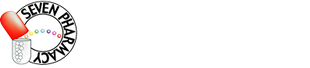1.新型コロナウイルスはどう怖いの?

先日、岡江久美子さんが新型コロナウイルス感染による肺炎でお亡くなりになられました。
人間の心理として、「あ~岡江さんは放射線治療もされていたから体力が低下されていたのかな。」と自分の体力との違いを見つけて、「ああ、自分は大丈夫」と思いたくなります。
「ちょっと熱っぽいけど大丈夫だろう」という人もいれば、
「あ~~37℃くらいだ。やばいかな~どうしよう!」と不安になる人もいると思います。
さて、原点に返ると、通常私たちが「風邪をひいた」という場合の15%がコロナウイルス(新型ではない既知のもの)とされています。また、それらのウイルスに対してはワクチンや抗ウイルス薬など存在しません。症状が軽症で済むケースが多いので「冬は風邪をひく」程度です。
今回の新型コロナウイルスは、通常の風邪と同様で軽症で済むケースが多いのですが、通常と違うのは「重症化した場合のスピードが速く、重症の程度がかなり重い」ことだと思います。
したがって、「軽症で済む体力があっても、ウイルス感染をしないこと」が今は重要になってきます。
2.熱っぽい?どうしよう?
熱の出方にはパターンがあります。
a) 体がだるくて37度~37.5度の間の微熱が出る
b) 急にゾクゾクと寒気がして数時間や半日で38度まで熱が上がる
インフルエンザや新型コロナウイルスなどが体内で急激に増えた場合は(b)になることが多いです。また、体の節々が痛くなる症状が伴うことが多いのも特徴です。また、サルモネラ菌などの細菌感染で腹痛などと同時に急激な発熱を起こす場合もあります。いずれにしても、「何らかのウイルスあるいは細菌に感染している状態」が多いのです。
a)の微熱の場合は様々な要因があり、微熱がでている期間も重要です。
肝機能が低下していたり、感染を起こしていても体力があってある程度細菌やウイルスを抑え込んでいる状態だったり、細菌感染でも膀胱炎、尿道炎、腎炎などの場合も急ではありませんが発熱を伴うことがあります。また、疲労症候群でも微熱が出ることがあります。
では、熱が出たときにどうしたらいいのでしょう?
大事なのは、熱が出る前の体調の確認が大事です。
*腹痛、下痢はなかったか? (細菌感染の可能性もある)
*トイレに頻繁に行っていたとか、残尿感はなかったか?また、尿が少し匂うこともなかったか? (膀胱炎や尿道炎、性器感染の可能性もある)
*朝がつらく、日中も体がだるい。朝は熱がないが、夕方以降にはじわ~っと上がってくる。(疲労症候群や肝機能低下などの慢性疾患、感染症を体力で抑えている状態の可能性がある)
細菌感染の可能性の場合はやはり病院にいって、医師の診察を受けて適切な抗生物質を処方してもらうことが必要です。また、病院に行った時に上記の情報を的確に伝えると、医師の先生も診断がやりやすくなるので聞かれなくても積極的に伝えることをお勧めします。
また、夜にじわ~っと熱が上がってくる場合は感染ではない場合もありますが、体力で感染源を抑えている場合もあるので、体力を低下させないことが大事になってきます。また、熱が続くと体力を消耗しますので、風邪薬や解熱剤なので熱や周辺の症状を抑えていく必要があるんです。
「早めのパ〇ロン」というのはこういうことなんですね。
風邪をひいたら早めに風邪薬を飲んで熱を下げて、体力の消耗を抑え、自己免疫がウイルスをやっつけてくれるのを待つ。
というわけです。
3.「4日間の過ごし方」
新型コロナウイルスに対する自己判断の目安として
発熱したら4日間様子を見るということが言われています。
でも、その4日間の過ごし方がその後の経過を左右するとも言えます。
*解熱剤や風邪薬でしっかり熱や咳、鼻水などの症状を抑え、体力の維持を図る
*栄養ドリンクや滋養強壮剤で低下した体力を戻す
*消化のいい食事を心がけ食べたものの栄養を体が取り込めるようにする。
*お酒、たばこは控える
*夜更かし、夜遊びをしない。12時までには寝る
*体を冷やさない。ビール、冷たいジュース、生野菜は控える
*体を温める食事:根菜、生姜、チキンやポーク、葛湯も◎
*カフェインを控える。(薬にカフェインが含まれていることが多いので)
*長湯をしない。(体を温めようと長湯をすると体力が低下します)熱めのお風呂でささ~~っと。早く体をふき、湯冷めをしないように。
4.病院へ行くタイミング
では、どこまで自宅で待機してどのタイミングで病院に行ったらいいんでしょう?
当薬局で相談を受けた場合でよく遭遇する状況は。。。
*風邪薬や解熱剤を飲んで1~2時間しても症状が治まらない
*3日間、薬を用法通り飲み続けても症状の改善が全く見られない
*熱以外の症状(咳、息苦しさ、のどの痛み、下痢、腹痛など)がひどくなってきた
*最初にはなかった症状がでてきた。(発疹、呼吸困難、)
などです。
上記はあくまで参考ですので、容易な自己判断は禁物です。かかりつけ薬剤師やいつも利用している薬局の薬剤師に電話で相談してみてください。
特に、慢性疾患などで常に服用している薬がある場合は薬の副作用なども併せて考えていく必要があるので、ぜひいつも薬をもらっている薬剤師にたずねてください。
保健所やかかりつけ医へ電話での相談が可能な方は、上記のような症状の変化などを医師に伝えて診察を受けるべきかの問い合わせをするのも方法です。

5.100%治る治療薬はどこにもないんです。。。
さて、ここで改めて薬剤師から皆さんに伝えたいことは
薬の効果は100%ではないということです。
ワクチンもそうです。副作用で死亡する可能性もあるわけです。
いま、治験をやっているアビガンも100%とは限りません。また抗ウイルス薬ですので副作用もかなりの頻度で発生します。副作用で亡くなる場合も今後発生する可能性もあるわけです。
抗インフルエンザ薬のタミフルでさえ、副作用で死亡した事例が55例あると報告されています。
6.今こそ「セルフメディケーション」
セルフメディケーションという言葉があります。
今回の新型コロナウイルスの発生で、セルフメディケーションの重要度が増したと思います。
それは、
「医療が必要な人に優先的に受けてもらうことが大切」
だからなんです。
また、薬だけでいうと
「医療保険で貰う薬の方の中にも市販薬と同等の効果、あるいは市販薬の方が複数の成分がまとまっていて効果がよい」ものもあるわけです。
もともと「医療保険で処方してもらう薬」というのは「医師の診断の元に使う必要がある薬」なわけです。
でも、実際には医療保険でもらえる薬の中に、市販の薬を同じ成分のものもたくさんあり、スイッチOTCといって「医療保険でもらわずに薬局で薬剤師に相談して買ってください」という基準に切り替わった薬もたくさんあります。
医療保険を使わず、市販薬を専門家である薬剤師に相談して購入することで医療保険の財源を使わずに済むわけです。その結果、今回の新型コロナウイルスだけでなく、命にかかわる病気で高額になる治療を医療保険でうけられる人を増やす…ことは今後の日本の医療では大切な考え方だと思います。
日本国民は戦後、ずっと国民皆保険に守られてきました。しかし、保険の財源にも限りがあります。医療機関にも、医療従事者にも、医療機器にも、医療材料にも、薬にも・・・限界があるんです。
医療崩壊という言葉は、単に「患者が爆発的に増えて大変な状態」というだけではなく、その「大変な状態」がありとあらゆる医療資源が枯渇になるのが医療崩壊なんですね。
「病院に行けば治る」
「医療保険を使えば大丈夫」
「保険で治してもらったら大丈夫」
という概念こそが、医療崩壊につながっているということを理解してもらえたらと思います。
そして、今一度
「自身の健康は自身で守る」ことが大切であること
そのために、日ごろから自分の体調を把握し、軽微な症状で市販薬で対応できる状況と、病院へ行く必要がある症状の見極めを専門家のアドバイスをもらいながら行うことが大切だということを理解してもらえたらと思います。
岡江久美子さんが自宅で数日様子を見ていたことを「どうしてすぐ病院にいかなかったのか?」という記事もネット上ではみられますが、これは後から批判するのは簡単ですが、現実の判断は難しいですし、「すぐに病院にいったら助かったのか」というのも難しいと思います。それは、誰にもわからないことだと思いますし、自宅待機の判断をされた医師も、専門家としてその時の症状や病歴、受けている治療の内容を鑑みて判断されたことなので、専門家でない人間が批判してはいけないことだと思います。
そして、今、もし、あなたや家族が微熱や体のだるさで不安だったら、これまで薬をもらったことのある薬局へ電話して、ぜひ相談してください。